2025.05.16 コラム
【チェックリスト付き】MCA無線終了に向けてすぐに始めるべき対応
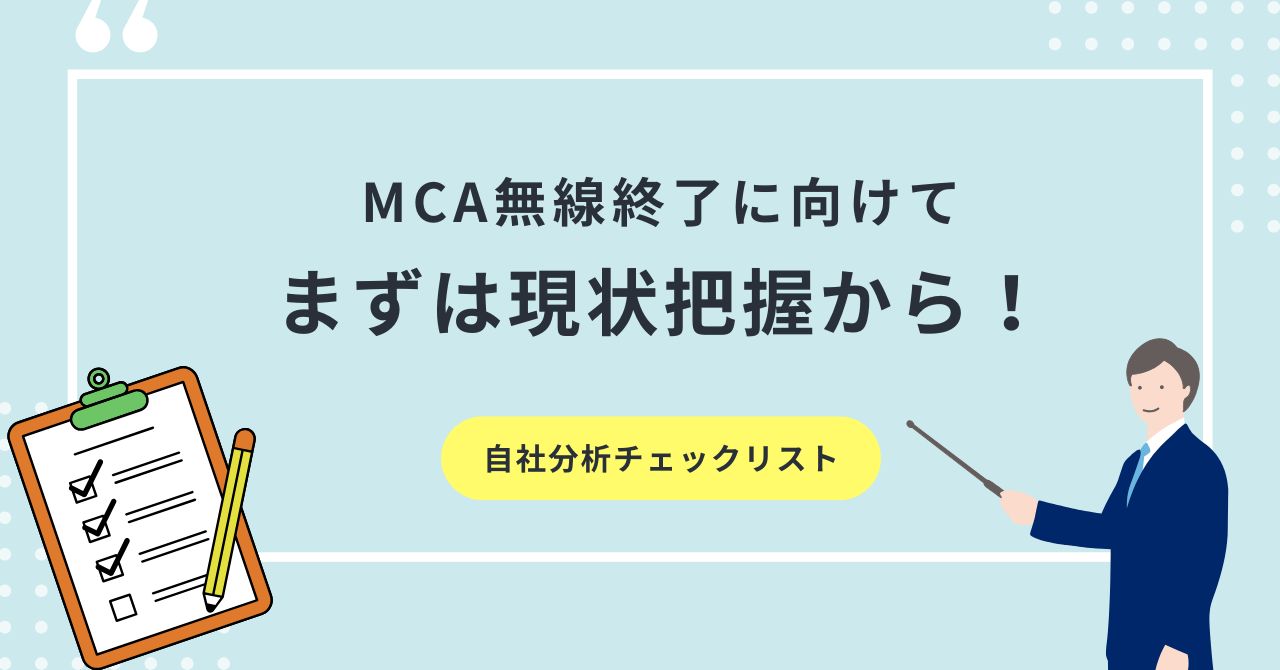
目次
「その日」は必ずやってくる──MCA無線サービス終了
2029年、デジタルMCA無線およびMCAアドバンスのサービス終了が正式に予定されています。長年、業務や防災で重宝されてきた通信手段が“使えなくなる日”が、着実に近づいています。
多くの企業で「代替準備はしているつもり」という認識がある一方で、実際には機器の整理や代替案の具体化が進んでいないケースが多く見られます。
特に情報システム部門や総務部門の担当者にとって、通信インフラの切り替えは手間も時間もかかるため、つい後回しにされがちです。
しかし、業務連絡や災害対応に使っていた通信が突然使えなくなる事態は、業務継続にとって致命的です。
「まだ大丈夫」と思っていたら、ある日突然“使えない現実”がやってくる──そんなリスクを回避するためには、今こそ現状の見直しが必要です。
本記事では、デジタルMCA、MCAアドバンス無線終了への備えとして必要な点を整理するチェックリストを掲載。
準備状況を見える化することで、自社の現在地を客観的に把握できます。
「まだ間に合う今」、まずは確認から始めてみませんか?
800MHz帯デジタルMCAサービス終了について-一般社団法人移動無線センター
MCAアドバンスサービスの終了についてのお知らせ-一般社団法人移動無線センター
まず必要なのは『現状把握』
MCA無線は、全国の防災・輸送・自治体業務を支えてきた、長年の通信インフラです。
中継局を用いた広域カバーと、同報通信による一斉指令。
地震や風水害といった非常時でもつながるこの仕組みは、行政機関から物流、交通業界まで、幅広く信頼を得てきました。
しかし、2029年にMCA無線はその役割を終えます。
このことは、通信手段そのものを失うだけでなく、業務オペレーション全体に影響を及ぼす可能性がある、重大な転換点といえるでしょう。
もちろん、代替手段は存在します。たとえばIP無線機やIP無線アプリ、スマートフォン、LINE連携型業務アプリなど。さらに、通信の冗長化を可能にするマルチプロファイルSIMなど、新たな技術も登場しています。
しかし選択肢が多いからこそ、かえって動き出せないという状況も多く見受けられます。
何を基準に選べばいいかわからない
既存端末の利用状況や台数が把握できていない
社内調整や予算化が先送りされている
特に、MCA無線が担っていた役割が明確に可視化されていない企業ほど、判断が難航する傾向にあります。単なる通話手段ではなく、業務連絡の即時性・一斉性・記録性など、独自の価値を持っていたMCA無線。
その代替を検討するには、機能・コスト・操作性・運用性の多角的な比較が求められます。
また、現場では「スマホがあるから大丈夫」という声も聞かれますが、実際には以下のような“見落とし”も起こりがちです。
スマホでの通話は1対1が前提で、複数人通話や即時の一斉連絡には向かない
運行や作業中の端末操作は安全性・効率の観点で制約が多い
部門ごとに導入形態が分かれており、全体での移行計画が立てられない
つまり、最も重要なのは「まず現状を把握すること」です。
判断するのではなく、事実を整理すること。何台、どんな用途、どの通信要件でMCAを使っているのか。これを可視化しなければ、代替策の検討は始まりません。
次章では、「準備が進まない理由」をより具体的に深掘りし、実務上のボトルネックを明らかにしていきます。
準備できているつもり”から抜け出すためのセルフチェック
MCA無線の終了に向けて、最も重要なのは「自社の今の立ち位置」を明確にすることです。
通信手段の見直しは複雑なテーマに見えますが、実は“知らないから動けない”というケースも多く見受けられます。
そこで本章では、MCA無線のリプレイス対応状況を確認するための簡易チェックリストをご用意しました。1つ1つの問いに答えることで、見えていなかった「見落とし」や「検討不足の箇所」が浮き彫りになります。
MCA無線リプレイス準備チェックリスト
- 利用中のMCA無線の機種・台数・設置場所が把握できている
- MCA無線の主な利用シーン(業務連絡・災害対応など)が整理できている
- 通話モード(個別・グループ・一斉)、録音の有無、動態管理の有無など通信要件が明確になっている
- 通信が使えなくなった場合に影響を受ける業務や部門の洗い出しができている
- IP無線やアプリ等の代替候補について情報収集を始めている
- リプレイス候補の機器の試験導入やデモンストレーションを実施したことがある
- 社内の関係部門と情報共有・調整が始まっている
- 予算化・社内稟議の準備に着手している、または完了している
- 通信の多重化や回線障害対策(例:マルチプロファイルSIMなど)の選定方針がある
- 「いつまでに、何をするか」といったスケジュール案が策定されている
診断結果の目安
8〜10項目クリア:準備は順調。実運用へ向けて具体化を進めましょう。
4〜7項目クリア:まだ検討段階。情報整理と体験(試験導入)を優先的に。
3項目以下:未着手の可能性大。まずは端末台帳と利用実態の洗い出しから。
このチェックリストは、あくまで“判断のきっかけ”です。完璧な準備でなくても構いません。ただ、点検することで初めて「動くべきポイント」が見えてきます。
次章では、このチェックの結果をもとに、準備状況に応じたアクションプランをご提案します。
対応状況に応じたアクションガイド
前章のチェックリストで「自社の現在地」が見えてきたら、次に重要なのは「何から手を付ければよいか」を具体化することです。
本章では、チェック結果に応じた3つのステージに分けて、現実的かつ実行しやすいアクションを提案します。
ステージA:8〜10項目クリア|「準備は整いつつある」レベル
この段階にある企業・団体は、すでに移行準備が順調に進んでいるといえます。今後はより実践的な検証と社内承認のフェーズに移行することが求められます。
推奨アクション
実機での業務シナリオ検証(例:一斉通話・グループ設定の確認、動態管理の運用確認)
通信環境やサービスレベルの安定性検証(エリアや地下環境など)
社内マニュアル・教育プランの作成とトライアル導入
ベンダーとの導入スケジュールのすり合わせ
ステージB:4〜7項目クリア|「情報収集中・検討中」レベル
検討は進んでいるものの、まだ判断や導入には至っていない段階です。情報を「整理すること」と「実物に触れること」が次の鍵になります。
推奨アクション
MCA無線の使用実態を再確認(非申告端末や予備機も含む)
代替候補のスペック比較表を作成(コスト・通話モード・操作性等)
ベンダーへの問い合わせ・デモ機体験の申込
社内関係者向けの説明会実施(部門連携のきっかけづくり)
ステージC:3項目以下クリア|「ほぼ未着手」レベル
「気づけば何も始まっていなかった」──多くの組織が最初に直面する段階です。この時期こそ、手戻りのない“正しい第一歩”が重要です。
推奨アクション
MCA無線と利用業務の棚卸し(リスト化・現場ヒアリング)
利用目的・業務上の必要性を明確に(通話頻度・緊急度・連携範囲)
選択肢の全体像を把握するための情報収集
まず1部門での小規模な試験導入を計画
すべての企業が同じ道筋をたどる必要はありません。大切なのは、「今の状態に応じた段階的アプローチ」をとることです。
準備が早ければ早いほど、選択肢も広がり、コストや導入負荷も抑えやすくなります。
次章では、このアクションを促進するための資料やデモ機の案内、問い合わせ窓口など、読後の具体的な行動につながる情報をご紹介します。
チェックから行動へ「まだ間に合う今」だからこそできること
ここまで、デジタルMCA無線およびMCAアドバンスの終了という現実と、それに対する具体的な備えのステップを整理してきました。
2029年の終了は避けられないものの、準備次第で“混乱”は“スムーズな移行”へと変えられます。
本記事の目的は、「まだ何も決まっていない」状態を「まず見直してみよう」という行動に変えることです。
まず、今すぐできることは「現状を把握する」ことです。
利用中の端末の数や設置場所、業務での利用目的、そして求められる通信要件。
これらが見えてくるだけで、自社に必要な代替手段の方向性が明確になります。
加えて、以下のような“小さなアクション”が、移行準備の起点になります
他社の導入事例や製品比較資料をチェックする
ベンダーに問い合わせてデモ機を取り寄せてみる
関係部署で情報共有会を開く
チェックリストを印刷し、社内で回覧する
本記事で使ったチェックリストは下記からダウンロードが可能です。
印刷・共有のうえ、社内での対話や計画立案にご活用ください。
ダウンロード資料・ご案内
代替機器についてじっくり相談したい方へ
「自社にどの機器が合うのか判断がつかない」「他社事例を詳しく聞きたい」といった個別のご相談にも対応しています。
用途・課題に応じた選定支援を無料で行っておりますので、以下よりお気軽にご連絡ください。
個別相談の申込はこちら:お申込みフォーム
通信の見直しは、単に機器を変えるだけではありません。それは、「業務の伝達手段」を未来に繋ぎ直すという、重要な見直しの機会です。
“知らなかった”で終わらせず、“準備していて良かった”と振り返れるように、今このタイミングで一歩を踏み出しましょう。
